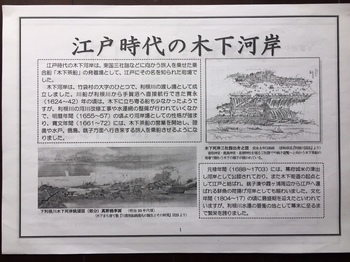社会教育の展望の最近のブログ記事
図書館の日本文化史
図書館について論ずるにあたり、図書館の内部の諸問題だけでなく図書出版・印刷はもとよりコンテンツとしての文学をはじめとする諸学術・芸術分野、その本や庇護にした人物などを幅広く視野に収める必要があると考えた
それらの歴史の累積が現代の文化に凝集、集積しているとの観点から、各時代の記述を等分には使わず、文字の年代から江戸出版業の確立までの歴史(古代から近世)を、第一章から第3章にまとめた
日本人は漢字という、日本文化とは全く異質な漢文化の表記文字である漢字を移入し、この漢字を利用することで日本文化を守り、使いやすくするため悪戦苦闘し、漢字の利用の仕方、読み方、判読の仕方のみならず、そこからまったく異質な仮名文字を生み出し、日本文化の初期化を日本文化に適切な形で完成させるという偉業を達成した
その結果、平安時代に国風文化が豪華絢爛に咲き誇る
後半部分では、幕末から20世紀の終わりまでを第四章、第五章にまとめ、第六章では、デジタル化に伴う技術革新により変化するだろう情報環境に影響される図書館の課題の若干についてまとめた
特に、第四章は、鎖国体制の中で帝国主義的な体制をとる西欧列強諸国に対し、立ち遅れた日本がどのようにそれら列強に短時間に追いつくことができたのか、という疑問への答えとなっている
その理由は残念ながら図書館が有効に機能したからではなく、江戸幕藩体制下での教育の高度な発展にあり、これが短い時間で西洋列強諸国に追いつくことを可能にしたと思われる
その後、満州国における権益をめぐる争いに端を発して日米の関係が悪化し、太平洋戦争が始まる
戦後、米軍の日本占領統治が始まり、米軍は日本を自由民主主義化するべく公共図書館の強化育成を試みたが、これは失敗する
しかし、日本図書館学校が設立され、国際水準での図書館専門職が育成されることにより、デジタル化時代において、情報管理体制の基盤を築くことが可能となった
また新書という形態の書幅の関係上、必要と思いながらも言及できなかったテーマも少なくないし、書き落としている課題もあろう。それでも一通り筆者なりの図書館についての総括したものである
パブリックコメントの意見が集約され、市HPに公表されました。
詳細は、PDFファイルをご覧ください。
更新日:2022年7月14日
習志野文化ホール再建設基本構想(案)に対する意見募集は終了しました
ご意見を提出された方、ご意見の数は以下のとおりです。
- 提出者:65名
- 提出件数:243件
いただいたご意見と市の考え方をお知らせします。
以下は、パブリックコメントを実施した際の内容です
図書館の未来について
欧米では、図書館のライブリアンと資料館のアーキビストは専門職で、
激動の時代、重要戦略のインテリジェンス(情報分析業務)を担っている。
ライブリアンは出版物の収集、保存、提供等の定型業務を通して、軍事、外交、生活・文化等の深層に訴えるアーカイビングの役割を果たしています。
日本では、図書館を勉強の場、あるいは資料の貸出しの場というイメージで、ハコもの行政の枠の中で、ライブリアンが官と行政の論理に縛られ、受け身になり、図書の貸出し係になり下がっている。
公共図書館を育てるとは、欧米や日本での議論や実践を踏まえて、
市民生活の場に見合ったアーカイビングを支援する図書館像を示し、
図書館は、現在、集客力の大きい公共施設なっているが、これに民間的な手法をおり混ぜることで、地域活性化に欠かせない「知的なクリエイティビティー」が醸成され、加味されることを期待したい。
-thumb-350x262-1522.jpg)
「社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない」(「教育基本法第12条」)わけである。
つまり法的には社会教育行政は学習支援をしなければならないことになる。
これまで社会教育行政は、社会教育施設の設置や、学級・講座の開設等による学習機会の提供、趣味・教養・スポーツ・レクリェーション等の文化活動やスポーツ活動の奨励、社会教育関係団体の行う活動や研修等の指導、助言等を通して広く民間の学習活動を支援してきた。
これらは全て学習支援と呼ぶことができる。
しかし、施設等のハード的側面ばかりではなく、「学習の質、成果を高める」「学習を通じて人と人とをつなぐ」「学習によって意識と行動が変化する」ための支援に主眼を置くことが重要である。
文化振興計画づくりを通して
「社会教育」を基盤とする文化振興計画になっていない、委託業者が体裁よくまとめられたように見える。
今後は、「施設再生計画」の齟齬った運用見解(社会教育施設体制等)を修正して、
「大久保の施設統合計画」についても教育委員会の社会教育推進施策がイニシアチブを取り、「公民館運営審議会」の答申、指針に沿い、今後の運営・事業展開を図ることを前提に、業者SPCへの指導対応をされたい。←三者協議会よりも上位体制が既に存在している。
さらに、公民館の指定管理委託について、すでに予算議決した以上は、公的社会教育事業推進の観点から「事業と管理運営」をきちんと区分けし
教育委員会の教育事業(専門主事による事業指導)活動(先表事業体系)の指導を図る体制をつくる。
施設活用レベル(貸出)の学習機会提案から、歴史・文化、そして現代的な課題に関する内容や、学び直しのリカレントの学習機会を、
もしくは、指定管理制度導入を根本から再検討することを提案します。
先進市が指定管理制度を社会教育施設に導入してない理由の研究をのぞみます。