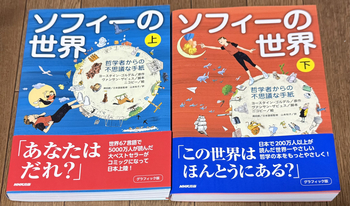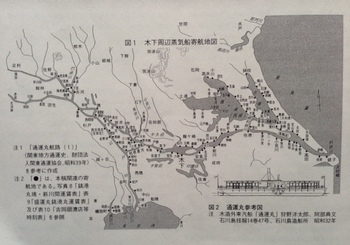「世界史の構造」→「力と交換様式」
柄谷行人 著 岩波書店
本の概要
1970年代後半から文芸批評家として活躍し、90年代後半からはマルクスやカント、ホッブスの読解から「交換」に着目した理論で社会や歴史を読み解いてきた柄谷行人さん。
その集大成ともいうべき『力と交換様式』では、社会システムを
A=贈与と返礼の互酬、
B=支配と保護による略取と再分配、
C=貨幣と商品による商品交換、
D=高次元でのAの回復
という4つの交換様式によって捉え、とりわけ資本主義=ネーション=国家を揚棄する、人間の意思を超えた「D」の到来をめぐって思考を深めた。
「Aの回復としてのDは必ず到来する」。
民主主義と資本主義が行き詰まりを見せる混迷の危機の時代、
絶望的な未来に希望はどう宿るのか。その輪郭はどのように素描可能か。
『世界史の構造』、そして『力と交換様式』を貫く「交換様式」の思考の源泉に迫る。

『世界史の構造』
柄谷氏は、氏族社会、古代国家、世界帝国、普遍宗教、近代国家、産業資本、グローバリゼーションへと世界史の流れを見渡し、「交換様式」から社会構成体の歴史を見直し、以下の4つの交換様式の変遷として整理する中から、現在の資本=ネーション=国家を越える展望を開こうと試みています。
交換様式A:互酬制(氏族社会)
交換様式B:略取と再分配(アジア型帝国、古典古代、封建制社会etc.)
交換様式C:商品交換(資本主義社会)
交換様式D:バージョンアップした互酬的交換(普遍宗教)
ごく平たく言い直すと、人間がつくる社会において、経済的関係のパターンは、贈与(贈り、贈られる)、略取(権力を背景に奪い、再分配する)、商品交換(お金を介して取引する)のいずれかになる。
そして商品交換の様式が支配的になり、その齟齬が大きくなった現代社会の先に、互酬的交換がバージョンアップした形態が登場することを予期している、という話です。
「力と交換様式」
柄谷行人氏流の唯物史観を分かり易く概説した本だと思います。
マルクスの『資本論』の中に、現段階の産業資本構造(社会構成体)の下部構造におけるキーコンセプトとして、生産様式だけでなく(多くの学者が見逃していた)交換様式が重要であることを明解に指摘しており、それを織り込んだかたちでこれからの社会変革の道筋を考察しています。
1970年代後半から文芸批評家として活躍し、90年代後半からはマルクスやカント、ホッブスの読解から「交換」に着目した理論で社会や歴史を読み解いてきた柄谷行人。
その集大成ともいうべき『力と交換様式』では、社会システムを
A=贈与と返礼の互酬、
B=支配と保護による略取と再分配、
C=貨幣と商品による商品交換、
D=高次元でのAの回復
という4つの交換様式によって捉え、とりわけ資本主義=ネーション=国家を揚棄する、人間の意思を超えた「D」の到来をめぐって思考を深めている。
「Aの回復としてのDは必ず到来する」。
史的唯物論に照らすと
- A=贈与と返礼の互酬: この交換様式は、比較的初期の社会形態である共同体や部族社会に対応します。こうした社会では、人々のつながりや信頼が贈与と返礼の互酬によって築かれます。結びつきが小規模で密接なものであるため、共同体の維持と発展が重要です。
- B=支配と保護による略取と再分配: この交換様式は、支配者と被支配者の関係が顕著な階級社会や封建社会に対応します。支配者が支配される者から資源を略取し、再分配することで社会的な秩序を保っています。こうした社会では支配と被支配の対立が中心となります。
- C=貨幣と商品による商品交換: この交換様式は、近代資本主義社会に特有です。商品交換や市場経済が中心で、個人の自己利益追求が活発です。資本主義の下では、生産の拡大や利潤追求が社会の中心に位置し、経済的発展が進行します。
- D=高次元でのAの回復:
この交換様式は、より広いスケールや複雑な社会においても、贈与と返礼の互酬の原則が活用されることを意味します。これは、大規模で多様な社会が共存し、結びつきを保つために、贈与と返礼の構造が適用されることを指します。
「力と交換様式」では、交換様式を通じて社会の変化を説明しようとしていますが、それぞれの交換様式が特定の歴史的な出来事に直接結びつくわけではありません。代わりに、これらの様式が異なる社会の発展段階や特性に対応し、経済的な要因が社会構造や関係に与える影響を理解しようとしています。
もし、特定の歴史的事象に関する詳細な説明が必要であれば、その事象に関連する具体的な歴史的文献や資料を参照することをおすすめします。柄谷行人の理論を歴史的事象に適用する場合も、その理論を基に考察を行うことになるでしょう
民主主義と資本主義が行き詰まりを見せる混迷の危機の時代、
絶望的な未来に希望はどう宿るのか。その輪郭はどのように素描可能か。
柄谷氏の独自の見方と立場が明晰に示されているユニークで貴重な書籍です。
「自由な思考」の典型例で、独自の視点で(通説とは異なる)未知の認知領域を探索する研究者にとって示唆に富む良書だと思います。
ただし、交換様式Dについて多くを望むと期待外れに終わるかも知れません。
未知の領域の開拓は若い世代に委ねられていますね。