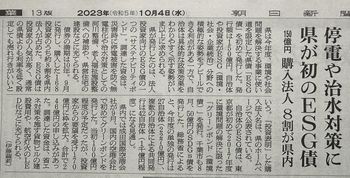経営戦略としての人的資本開示 日本能率化協会マネジメントセンター
内容紹介
今日の株式市場において、ESG要素を重視する世界中の投資家は、企業価値創造の源泉である「人的資本」への開示圧力を強めています。そこで、本書では、ESG投資家が情報開示を切望する「人的資本」が国内外の政治経済の動向にどのような影響を与えているかを概観し、この動きが日本企業にとっても不可避な潮流であることを解説します。
人的資本経営におけるリーダーシップ、エンゲージメント、タレントマネジメント等の国内外の取組み事例を引用し、体系的にわかりやすく理解できるガイドブックです。
【目次】
序 章 人的資本の開示と企業価値の向上
第1章 資本主義の大転換―人的資本が企業価値の源泉になる第2章 人的資本開示の世界的潮流―欧州、米国、そして日本
第3章 人的資本経営の実現とHRテクノロジーの活用
第4章 会計学からのアプローチー無形資産の価値をどう捉えるか
第5章 人的資本開示分析の方法論
第6章 企業価値向上のための3つの提言
事例編 ドイツ銀行/バンク・オブ・アメリカ/スターバックスコーヒー/日立製作所/楽天グループ
はじめに
序 章 人的資本の開示と企業価値の向上
1 2022年は「人への投資の開示」元年
2 人的資本開示の衝撃 ──その背景で起きている3つのメガトレンド
3 人的資本経営と人的資本開示の関係性
4 人的資本経営とこれまでの経営との違い
5 人的資本経営の指標を選ぶ際に重要な3つのこと
6 人的資本経営におけるKGIとKPIの体系化
7 人的資本の開示が企業価値向上につながるわけ
第1章 資本主義の大転換 ─人的資本が企業価値の源泉になる
1 人的資本報告の国際規格開発と普及促進
転機となったリーマンショックによる潮流の変化
人材マネジメントにおける国際規格開発──新時代の幕開け
ISO 30414を普及促進するグローバルネットワーク
サステナビリティ開示における人的資本開示
2 ESG/サステナビリティ投資家が求める人的資本経営の本質
産業構造の変化による人的資本の重要性の高まり
日本企業の企業価値に占める無形資産価値
人的資本経営におけるデータ活用
人的資本経営における主要KPIの例
第2章 人的資本開示の世界的潮流 ─欧州、米国、そして日本
1 欧州連合(EU)の人的資本開示に関する動向
欧州連合1 非財務情報開示に関する欧州議会・理事会指令
欧州連合2 「報酬の透明性」の開示
イギリスは独自の人的資本開示強化を推進
女性活躍の先頭ランナー──アイルランドの人的資本開示
2 米国の人的資本開示に関する最新の動向
米国証券取引委員会による30年ぶりのルール改定
法整備を進める米国連邦議会──人への投資開示法0
3 急ピッチで追い上げる日本 ──2021年以降の政策動向
失われた20年を取り戻すための政策の系譜
コーポレートガバナンス・コード改訂で強調された人的資本の開示
岸田内閣の掲げる「新しい資本主義」と人的資本の開示ルール整備の動き
第3章 人的資本経営の実現とHRテクノロジーの活用
1 リーダーシップ
リーダーシップ領域は人的資本開示の最重要テーマの1つ
「リーダーシップに対する信頼」の可視化が組織を強くする
HRテクノロジーの実践活用
他の項目との関連性
2 後継者計画
真のタレントマネジメントとは
後継者有効率
後継者準備率
HRテクノロジーの実践活用
他の項目との関連性
3 タレントマネジメント(採用・異動・配置)
雇用あたりの質
内部異動率
HRテクノロジーの実践活用
4 スキルと能力
労働力のコンピテンシーレート
HRテクノロジーの実践活用
5 ダイバーシティ
コーポレートガバナンス・コード改訂におけるダイバーシティ&インクルージョンの扱い
年齢、性別、障害およびその他の要因に関する労働力の多様性
リーダーシップ/マネジメントチームの多様性
世界の最新潮流と我が国の状況
6 人的資本経営の根幹を支えるHRデータ&HRテクノロジー活用プラットフォーム
日本企業の多くが陥っているレガシーシステムの罠
世界標準の人的資本経営を支えるHCMクラウドの実際
第4章 会計学からのアプローチ ──無形資産の価値をどう捉えるか
1 人的資本経営とファイナンスの関係
見えざる資産の情報開示
ステークホルダー別Pros&Cons
人財価値を会計的に捉える
人材と人財の定義
人財バランスシート(B/S)の活用
2 インタンジブルズ─見えざる資産─とは
人的資本を見つめなおす
インタンジブルズと人的資産04:42
会計学におけるインタンジブルズの特徴とその扱い
統合報告における開示の状況
人的資産の測定における会計学アプローチとその特徴
これからの人的資産の管理・測定・開示
第5章 人的資本開示分析の方法論
1 人的資本の開示を可視化する
データソース
測定方法
人的資本の開示度の可視化──HCDIレーダーチャート
2 人的資本の開示状況を把握する ──HCDIを用いた分析
3 HCDIの留意点と今後の日本企業の課題
第6章 企業価値向上のための3つの提言
1 「人的資本の開示」の定義
2 「人的資本開示の実践」のためのフレームワーク
3 人的資本開示の実践に向けての3つの提言
提言1:経営者と人事部門による「ナラティブ」な説明
提言2:HRデータ&HRテクノロジー活用の推進
提言3:「中長期的視点」での時間軸の重要性
人的資本経営における「人事中計」策定のススメ
事例編
■ 米国企業の人的資本開示のトレンド
米国におけるルール改訂後の動向
ハーバード・ロースクールによる調査でわかったこと
CASE 1 人的資本開示の先駆的役割/ドイツ銀行
CASE 2 米国初の人的資本開示/バンク・オブ・アメリカ
CASE 3 『サステナビリティレポート』を公開/スターバックスコーヒー
CASE 4 人財戦略に関する情報開示施策への注力/日立製作所
CASE 5 『コーポレートレポート2020』による開示/楽天グループ